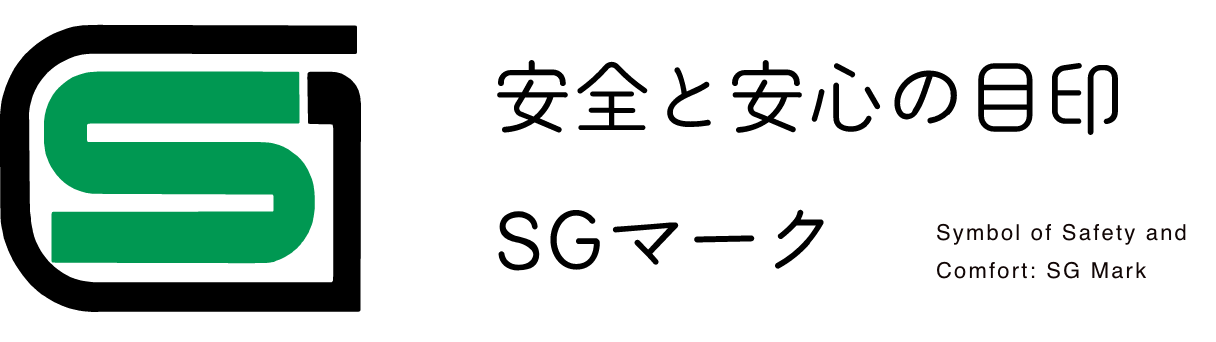Newsお知らせ
お知らせ
2024年04月26日
四半期毎のSGマーク表示数量
お知らせ
2024年04月24日
キッズ向けコンテンツ『SGマークって、なあに?』YouTube動画を作成しました
リコール情報
2024年04月19日
SG基準不適合 非木製バットのリコールについて
お知らせ
2024年04月26日
四半期毎のSGマーク表示数量
お知らせ
2024年04月24日
キッズ向けコンテンツ『SGマークって、なあに?』YouTube動画を作成しました
お知らせ
2024年04月18日
SGマーク付き製品 Products with SG Marks(2024/4/18更新)
リコール情報
2024年04月19日
SG基準不適合 非木製バットのリコールについて
リコール情報
2021年05月24日
ベビーカー自主回収のお詫びとお知らせ
リコール情報
2021年04月16日
ベビーカー車体フレーム無償交換のお詫びとお知らせ
SGマーク基準
2024年03月28日
「家庭用の圧力なべ及び圧力がま」SG基準改正について
SGマーク基準
2024年01月15日
衝撃緩和帽のSG基準改正について
SGマーク基準
2023年12月01日
自転車等用ヘルメットのSG基準改正について
SG Mark SchemeSGマークについて
SGマーク制度や、表示基準など
SGマークに関する
基本的な情報をご紹介します。
Application申請手続きについて
SGマークを表示するための
各種申請手続きについて、
ご紹介します。